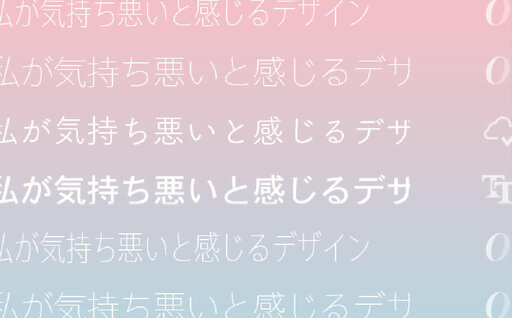Web 1.0 とインターネット民芸
皆さん、こんにちは。
皆さんは、インターネットの黎明期、Web 1.0 の世界を体験したことはありますか?2000年代前半、当時は今の情報過多の時代とは異なり、情報といえばTV、雑誌、新聞、ラジオなど。メディアの影響がかなり強く自分から行動しないと情報は得られないという感じの時代でした。着々とインターネット老人になりつつある私が今回お伝えしたいのは、私が見たWeb 1.0 の世界を振り返りつつ、「インターネット民芸」という造語を通して、初期のインターネットがある時期に再びどうして注目を集めたのかを書いてみたいと思います。
「インターネット民芸」とは何?
美術手帖の記事によると
「インターネットミームを柳宗悦の『民藝』に見立てたもので無名の個人が作り、広がるミームの素朴な魅力と、それが企業や国家に利用され、本来の「無銘性」が失われていく歴史を考察しています。過去の民藝運動と重ね合わせ、現代のインターネットの課題を浮き彫りにする評論です。」
とのこと
私が実際に見て、聴き、感じたところとしては、平成中期のインターネット特有の、懐かしさを感じる画像やグラフィックが再びフィーチャーされた現象を指していると言葉から感じました。イデオロギーの話とはあまり関係なく単純に誰もが簡単に創作し、ネット上に無数の創作物が溢れていたような気がします。
民芸品といえば「手作り感」「素朴さ」そして「無名の作り手」。そしてついツッコミを入れざるをえない用途のわからない木喰仏。これらは小・中学生のときに旅先で遭遇した、木彫りの熊の置物や木刀、よくわからないペナントや提灯、はがきなどに似ていると感じたのです。インターネットの特徴も相まってそういう意味で私はインターネット民芸と呼んでいます。
私が体験したWeb 1.0 (2001年〜2004年頃)
私がインターネットに本格的に触れ始めた大学時代(2001年〜2004年頃)は、まさにWeb 1.0 の真っ最中でした。当時はまだ、ADSLが普及し始めたとはいえ自宅の接続は「ダイヤルアップ」でした。懐かしい「ピーヒョロロロ...」という接続音とともに。回線速度も今とは比較にならないほど遅く、画像一つ表示されるにも時間がかかりました。
この時代を最も象徴するものは個人サイトです。今のように手軽なSNSもブログサービスもない中、誰もがHTMLを学び、自作のウェブサイトを立ち上げては、思い思いに情報や創作物を発信していました。情報が少ない時代に個人的に海外情報や独特の視点で情報発信してくれる、サイトは本当に貴重でした。BBS(掲示板)は活発な交流の場となり、匿名性の中にも確かに「個人の顔」や「手作り感」があったように思います。ネット上ではテキストと粗い画像、Gifアニ、そしてMIDIなどがWebコンテンツの中心でした。
全く顔も知らない人とネット上で会話が成立したときの感情はなんとも表現しがたい思い出があります。
今から見れば、機能面では非常に不便でした。しかし、それが逆にインターネットを探検する楽しさや、苦労して目的の情報や面白いコンテンツを見つけた時の喜びにつながっていたような気がします。
Vaporwave
それから10余年、2016年頃、私は突如Web 1.0 的な特徴が再注目されるムーブメントがネット上で起こっていると感じました。その代表的な例の一つが、Vaporwave(ヴェイパーウェイヴ)というカルチャーです。
Vaporwaveは、2010年代前半にインターネットの音楽コミュニティから生まれたジャンルで、2010年代半ばにかけて大きな広がりを見せたと言われています。1980年代から1990年代のポップスや店内BGMなどをスローダウンさせたりループさせたりする独特な手法の音楽ジャンルです。その聴覚的な体験は全く聞いたこともない新しいジャンルに聞こえました。だけどフレーズとしてはどこか聞いたことがある特徴も併せ持っています。
視覚的には紫や水色、ピンクを基調としたネオンカラー、粗いピクセルCG、塑像、グリッチ。そして意味を持たない日本語の断片。当時Webサイトのチープさや、Windows 95/98といったOSのグラフィック(特にWordが顕著)、初期3Dゲームのビジュアルを模倣しそれらを破壊したような特徴がありました。そのせいか、どこか薄気味悪いのも特徴です。Vaporwaveは単なる懐古趣味に留まらず、インターネットの商業化に対する風刺、批評の現れだと思います。私もWeb業界の人間として使いやすいサイトとはなんだろう?人に伝えるとはなんだろう?と考えながら仕事していますが、着地するところは同じような結果になることが多いです。人が使うのだから同じようになって当たり前だと思っていましたが、Webとはまるで違う世界観で自由な発想で展開されるSNSに毎日釘付けでした。
このVaporwaveムーブメントを目撃した時、まるで過去のインターネットが現代に蘇ったかのような感覚を覚えました。それは、SNSの「映え」や情報の最適化が進む現代のWebとは全く異なる、匿名性の中で純粋に表現を追求した、独自の文化形成をしていたあのWeb 1.0 の精神へ回帰しているようにも感じられたのです。ここで、私が当時創作したものやVaporwave臭を感じる品をいくつか紹介します。

Web 1.0 とインターネット民芸が現代に問いかけるもの
Web 1.0 と「インターネット民芸」は、現代Webに対して、新しい価値観を提示してくれたような気がしました。美術手帖の言葉を借りるなら「無名の個性」です。完成度が高くなくても、技術的に未熟でも、作り手の感性があればそれで誰かに伝わる。そして、情報が厳選されていなかったからこそ、偶然の出会いや発見の喜びがあったように感じます。
現代のインターネットでは、ふとしたことで炎上するリスクから、細心の注意を払った表現が求められがちです。しかし、そうした制約の中で、「これが素晴らしい」「これが美しい」と素直に表現することの重要性を、私たちは見つめ直すべきではないでしょうか。
「インターネット民芸」は、効率や利便性だけではない、インターネットが持つ表現の可能性を教えてくれました。簡単に言えばサンプリング文化ですが、亜流を通してオリジナルの価値を再発見できるように感じます。
まとめ
Vaporwave に端を発したインターネット民芸は、仕事づけで視野狭窄した私に単なる懐かしさで語れない現代のインターネットが失いつつある「個性」と「自由」を教えてくれたような気がしました。また、オリジナルを知るきっかけにもなったりしています。
最近では少し廃れてきたような感じがします。しかしまた流行る時が来るんだろうななどと考えるとまた老人に一歩近づいたような気がしてくるのです。
関連記事
お仕事のご相談、採用についてなど、お気軽にお問い合わせください。